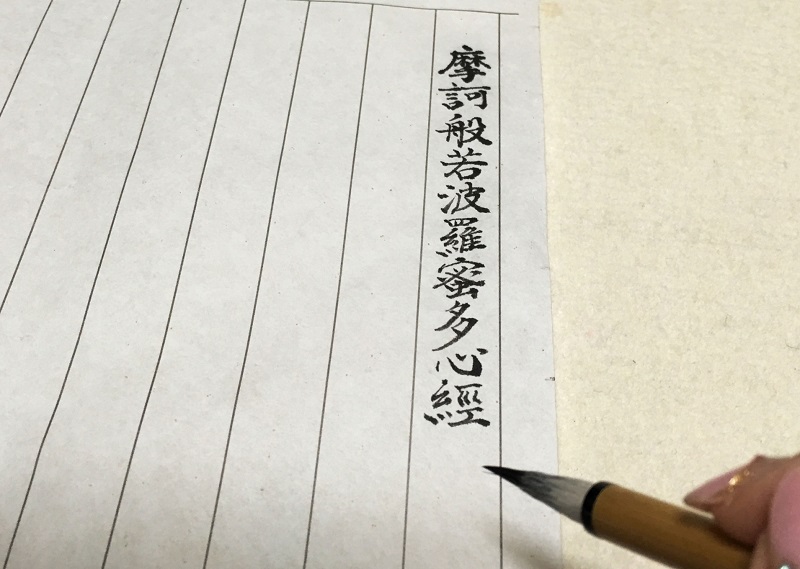2018年5月– date –
-

ドラマチックな恋物語のヒロイン・額田王
はじめに 『万葉集』に十数首の歌が掲載されている額田王(ぬかたのおおきみ)。 飛鳥時代、額田王は皇極天皇に采女(女官のこと)として仕えていました。 才能豊かな額田王は皇極天皇(こうぎょくてんのう)に重宝され、皇極天皇の息子である大海人皇子(の... -

海軍士官の食事は豪華だった!!その理由は??
はじめに 海軍の食事、といえば「カレー」がとても有名です。 曜日の感覚が狂いやすい洋上勤務において、毎週金曜日にカレーを出すことで一週間という期間を感じる目安にしたともいわれ、現代の海上自衛隊でもこの「金曜カレー」の伝統を引き継いでいます... -

苦労の幼少期から、上位の地位へ。浅井江の歩んだ人生。
<出典:wikipedia> 1567年。 お市が兄・織田信長の命令で浅井長政に嫁ぎ、三姉妹が生まれました。 その末っ子が浅井江でした。 やがて長政と信長が対立すると、1573年。 江の父親・長政は切腹してこの世を去り、お市と三姉妹は、織田信次の守山城で暮ら... -

幕末の大人物を輩出した名流派!「直心影流剣術」
はじめに 武士にとっての剣術は、自己防衛の手段というだけではなく、心身を練磨して真の強さを身に付ける修養の道でもありました。 古来より、すぐれた剣術流派はただ単に敵を打ち倒すだけではなく、人格や品位を高めていくことを教える崇高な哲学でもあ... -

武士の「裏芸」 超マイナー武器術3選!
はじめに 武士にとっての表芸は剣術。 戦場においては弓馬の術に槍などの長柄物が主兵装で、素手においては柔術で闘うなど。 いわゆる「武芸十八般」と呼ばれる武器術や格闘術を修めることが武士にとって必須とされてきました。 日本の武術は剣術を... -

日本最古の校正者たち。東大寺の校生!!
はじめに 各種の申込書や履歴書、仕事での資料など、わたしたちの日常には多くの文書があふれています。 なかには絶対に記載内容が間違っていてはいけないような重要なものもあり、必ず正誤をチェックしなくてはなりません。 そんな作業を「校正」といい、... -

チタタプ、ルイベ、シト。北の大地・アイヌの伝統グルメ!
<出典:ほんのひきだし> はじめに 北海道を中心とした日本の先住民族、「アイヌ」の人たち。 現在でもその末裔の方々が、伝統文化を継承しています。 古くから日本本土の和人との交流が盛んだったアイヌ民族は、様々な点で日本の影響を受けていま... -

巌流島の由来は佐々木小次郎!謎多きその生涯に迫る
巌流島には「決闘の聖地」なるキャッチフレーズがついています。 巌流島の決闘が繰り広げられたことにちなんでですが、当時は船島と呼ばれていました。 現在でも正式名称は「船島」で、住所も山口県下関市大字彦島字船島です。 1612年4月13日。 宮... -

高杉晋作と萩の城下町!古地図でわかる桂小五郎・伊藤博文との関係
萩市内にはたくさんの夏みかんが色付いています。 城下町の面影が色濃く残る界隈には「夏みかんソフト」「夏みかん漬け」「ホット夏みかん」… とにかく夏みかんです。 この夏みかんは明治維新後に栽培されるようになりました。 幕末。 長州藩の政治... -

「長州男児の腕前お目に懸け申す」功山寺で高杉晋作が挙兵!
1865年1月12日、降りしきる雪の中。 功山寺山門にたたずむ高杉晋作は、白く染まった石段を見下ろしていました。 『国を売り君をとらえて至らざるを無し、忠臣義に死すこれこのとき、天祥の高節成功の略、二人を学んで一人と作さんと欲す』 (国を売りながら...